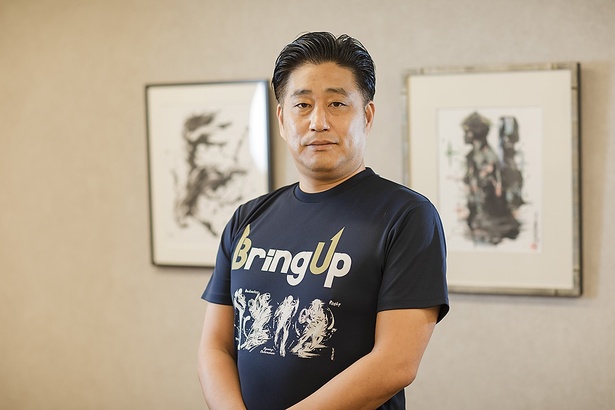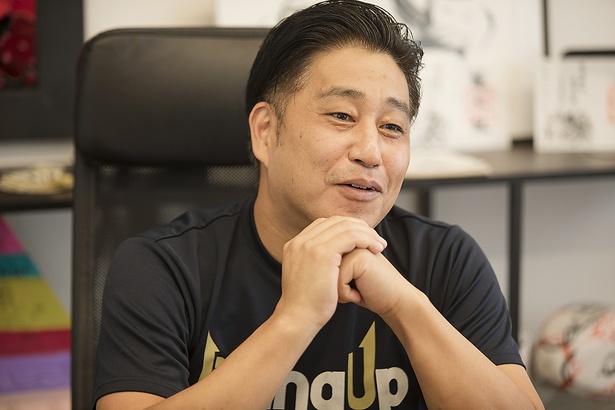ーー今回の取り組み方には、何かアイデアのヒントがあったのですか?
【岸本公平】実は、以前にも、この御朱印プロジェクトに近い内容でビジネス展開をしたことがあるんです。ただ、それは失敗しました。経済性が生まれると、ステークホルダーのこともしっかり考えないとマズいということを身をもって学びました。SDGsという言葉が広がるちょっと前の話ですが、ローカルtoローカルとして、長野県飯田市の水引を高付加価値商材に加工して、福岡県で販売する営みに挑戦しました。飯田市には、水引を作る匠の技があるのですが、技術伝承の後継者問題を抱えて縮小傾向にありました。そして梅が県花の福岡県は水引の伝統的な結び方の梅むすびと相性がいい土地柄で、なおかつインバウンドも含め観光客を呼び込む地域だったんです。さらに、その商品化工程の一部を知的障害を持った方たちが働く、就労継続支援B型事業所にもお願いしました。
ーーその意図は?
【岸本公平】障害を持った方の、ある姿を目の当たりにしたのがきっかけです。それは、障害を持った方を交えた酒席で、「これ、僕が刺した豚バラだよ」と、テーブルに出された豚バラ串を指して言うんです。僕らからしたら、誰がどう刺した串かわからない。でも、彼はそれを誇ったんです。「おいしいでしょ。僕が刺したやつだから」って。その姿を見たときに、決して高くはない工賃と2カ月に1回の障害者年金というギリギリの収入ではなく、誇れる仕事で自立できる工賃が払える環境を作れないだろうかと心を揺るがされたんです。そして、作業工賃の時間あたりの単価を今よりも上げた想定で支払うと、彼らがある程度自立できるという数字が組めました。
【岸本公平】そういうわけで、その商品は、“就労支援や匠の技を持った生産者さんに還元する”という、付加価値をつけたモノでした。お客さんには価値あるものを選んで買ってもらえるし、それに関わる人たちも誇れる仕事ができるという内容だった…はずなんです。

ーー失敗してしまった、と。
【岸本公平】はい。関係する事業者さんのなかの1社が自社の利益率のみを追求したために、伝統を守る水引職人さんからの原材料をいかに安く仕入れるかにこだわってしまう事態が起こりました。結局、水引職人さんが「数は出るけれど続けるのはきついよね」と圧迫されてしまったんです。持続可能が本質的な部分だったのに、会社としての“おいしい収益源”と考えてしまった人がいたため、持続可能ではなくなってしまったんです。自分さえよければいいと考える事業者さんがいると、どうしようもないですよね。僕がそういうステークホルダーに対して、取り組みの意図をしっかり伝えきれていなかったことが、そのときの失敗の原因だと考えています。
ーー共通の理念・目的より自分の利益を優先するステークホルダーがいると崩壊してしまう、と。
【岸本公平】はい。そんな失敗を経験していたので、今では、製造から最終的に消費者に届くまでに関わるステークホルダーを一堂に集めて、必ず理念の部分をしっかり共有するようにしています。そして、いきなり収益事業として始めるのではなく、まずは理念やビジョンの共有から始めるので、パートナーも必死に継続するんです。やっぱり、ボランティアだと長続きしないので。それぞれ商売上は直接関係ない会社ですが、「続けるために、これは大切だ」と思ったら、ステークホルダーたちが必死になって「困るから仕事を作らなきゃいけないよね」っていう構造になっています。つまり、続けるための手段が経済活動と一体になった仕組みになっているんです。
【岸本公平】その代わり、事業として高収益化できるまでには時間が掛かり足が長いことは良くあります。プロジェクトを立ち上げてからステークホルダー各社が納得できる黒字化をするまでに5年掛かったというようなこともあったりします。ただ、ブレない一体感で取り組むため、ある目的に対しての手段が成長し続けるものになります。
ーー理念やビジョンがズレない形を、まずそこで作らないといけないということですよね。
【岸本公平】「誰がいくら儲かっているのか」を、関係者は全員が知っている形にしています。ですから、文字どおり、透明性のある事業ができているんです。この手法がうまくいくと、お互い同じ考え方で、次に何ができるかアイデアを出したり、共同で拠出をしてくださるようになります。つまり、プロジェクトに対しての先行投資や、周知啓蒙のための事業企画が生まれる広がり方ができるんです。
九州一小さな町が大胆なSDGsを実装!ローカルtoローカルによる脱炭素ストーリー
ーー御社が取り組むローカルtoローカルの取り組みについて、ほかの事例も教えていただけますか?
【岸本公平】福岡県に吉富町という、九州で一番小さい町があります。人口約6000人の小さな町ですが、以前は製薬会社の本社工場のある企業城下町でした。ところが、その本社が合併して移転してしまったので、ただの人口密集地になってしまったんです。そして、2020年にゼロカーボンシティの取り組みが全国の自治体で始まったときに、この町はカーボンニュートラルの取り組みができませんでした。なぜなら、町のほとんどが宅地で、太陽光パネルを張る土地もなければ森もなく、土地の登記で山林がゼロだったからです。そこで、SDGs17番目の実践として、官民連携パートナーシップによる3社間での包括連携協定を締結しました。ここでは株式会社シェアリングエネルギーさんと一緒に取り組むことで、東京の会社と地方都市のローカルtoローカルの循環モデルを確立し、賛同企業や団体が集まった分だけプロジェクトが大きくなる仕組みになっています。


ーー具体的にはどういった取り組みを?
【岸本公平】まず何をしたかというと、公共施設や一般住宅に太陽光パネルを無償で設置しました。しかも財源として税金を使うのではなく、民間のエネルギー会社から最大36億円をESG投資によって確保したんです。これによって、年間予想発電量約10.5万kWh相当、年間約47tの二酸化炭素を削減することが可能となるプロジェクトを立ち上げることができました。2023年3月の時点で山林0の町が実装ベースで二酸化炭素の削減効果を東京ドーム5杯分の9万キログラムの削減の実現に成功し、自治体と住民が一体となる取り組みでの脱炭素社会の実現と住民個々の自分ごと化にも成功することができました。さらに、設置から10年の契約満了後には太陽光パネルは無償譲渡され、売電益は吉富町と導入をした住民に各々入ることで、脱炭素の推進による自治体の自主財源の獲得と導入した住民の所得となり、独自の新たな地域での収益モデルも構築することができました。
【岸本公平】次に、脱炭素を加速させるために動き始めた事業が、吉富海岸再生プロジェクトです。海岸に漂着する海洋ゴミを集めて資源化を目指しています。今までは誰が捨てたかわからないゴミの処理に町の税金を使うわけです。すると「人のゴミを税金で処分するな」と批判も生まれたりするはずなんです。でも、この町のすごいところは、こうした意識が高いというところ。町長さんが、そういうところに力を入れていて、学校教育の場でも教えているんです。きれいにするだけでなく、さらに経済性を持たせるために資源化に取り組んでいる。日本には離島が多く海岸も多いので、この事業モデルが広がっていけば脱酸素の推進になりますし、環境保全にもつながると思います。しかも、この取り組みの財源は、企業版ふるさと納税なんですよ。賛同してくれた企業さんからすると、税金を納めることでSDGsの社会実装に寄与できるので、CSRにもつながります。さらに、その事業の分野でのリーディングカンパニーとして旗振り役になれるというメリットがあるので、しっかりとした収益事業になるんです。実は、ここが一番大きいポイントです。

ーーローカルtoローカルを軸にSDGsがうまく浸透していますね。この実例を目の当たりにしたら、確かにほかの企業も賛同したくなる気がします。
【岸本公平】そうですね。今後、新しいビジネスモデルとして、たとえば、災害対策だったらドローンの会社さんに声をかけたり、海洋ゴミなら海洋ゴミを再資源化する会社さんとか、目的に合わせて専門の会社を紐づけるのが、僕が今一番やるべきことだと思っています。役に立つし、地域に産業集積もできるし。こうしたプロジェクトを進めさせていただいているのは、SDGsの社会実装を、企画とチームビルドの力で推進していけると確信したからなんですね。この町は“九州で一番ちっちゃい”っていうキャッチーさもありますし。
ーーこうした取り組みを通じて、御社が実現したい未来、社会ついて教えていただけますか?
【岸本公平】今までは、日本の国力の強さや観光客インバウンドがありましたが、以前のような強さはすっかりなくなりました。そうした背景もあり、地方創生に対して強く思うところがあります。こう言っては各自治体に失礼ですが、「諦めている」というか「自分のところではどうにもできない。経済活動ができるわけない」と思っているところが多い。そうした思いがあるがゆえに、可能性にすら気がついていないんです。だから地方はこれまで勝てなかったんですね。
【岸本公平】ですから、これからはもっと地方から日本の魅力を発信して、一緒に勝たせていただきます。弊社がビジネスとして成功するということは、その地域も勝ったことになるので、まずは伴走させていただいて、パートナーと一緒にビジネスモデルを日本中に浸透させていくことですね。そうあるべきだと思って、今、吉富町でしっかり向き合わせていただいています。
取材=浅野祐介、取材・文=北村康行、撮影=樋口涼